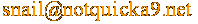今日もいつものように科学大好き土よう塾を子供と見ました。
その中で、花火について面白いことを話していたので、調べてみました。
花火というのは戦国時代、鉄砲伝来と同時に火薬の娯楽として日本に伝わりました。当時、花火の色は白黒の濃淡のみのモノクロ花火でした。それでも、当時の将軍たちの間では大ブームになったそうです。
明治に入り、横浜にマッチの原料として塩素酸カリウムが輸入され、これを日本の花火に応用し、色付花火の研究が始まりました。江戸時代、暗い炭火色の花火しか見ていなかった人々は、初めての華やかな色彩の花火に大変驚き、感激したそうです。
今では色数も増えて、あんなカラフルな花火ができるようになりました。
色をつけるには化学反応を利用します。火薬と一緒に添加する薬品の種類により、発光色が変わります。 
- 赤・・・ストロンチウム
- 青・・・銅
- 緑・・・バリウム
- 黄・・・ナトリウム
- 金・・・チタン合金
- 銀・・・アルミニウム
基本はこの程度、後はこれらを混ぜ合わせて中間色などを表現します。
銅、アルミなどは割と想像つく色ですが、驚いたのは、なんと緑にバリウムが使われていることです。バリウムといえば、あの人間ドックなどで飲むまず~いやつです。今まで、あれはなんだべ?って思っていましたが、あれも立派な科学薬品なんですねぇ。
チタンなどは近年、私の携わる切削加工でも良く使われるようになりました。細かい切り粉などが刃物との摩擦で熱くなると、まれに燃え上がり、ものすごい勢いで発光します。
チタンが花火に使われていると聞き、あぁそりゃ、ありえるなぁと思いました。
また、夏が近づき、花火の季節になってきました。
我が家は運の良いことに、東京湾、多摩川、ちょっと離れて横浜までの花火が屋上から見えます。
花火のこと、ちょっとお勉強した今年は、家の屋上から花火を観るのが今から楽しみです。
Popularity: 4% [?]
Posted on 7月 3rd, 2004 by snail
Filed under: TV&Entertainment | 4 Comments »